店長研修のカリキュラムはどうやって決めているのですか?

店長研修のカリキュラムはどうやって決めるのか?という質問を最近よくいただくのでコラムで公開します。
基本的に問い合わせをいただくのは企業幹部もしくは社長から連絡をいただきます。店長研修の多くが紹介なので、紹介先のクライアントからある程度の課題感は聞いたうえで打ち合わせの席を設けていただきます。
私はまず本社(経営層)側から話を聞きます。質問項目も30項目ほどあり、現状の経営課題から人材に寄せる期待などを細かくヒヤリングします。
ヒヤリングが終わったらカリキュラムを作る、というわけではなく基本的には現場のヒヤリングをします。この現場ヒヤリングは初回の研修当日に数名にヒヤリングすることもありますし、事前に店舗に伺ってヒヤリングの時間を設けて話をします。
基本的には本社側が把握している現場の課題と現場が課題に感じていることに大きなギャップがあります。
・企業成長している→現場と本社の課題感のずれが小さい
・企業衰退している→現場と本社の課題感のずれが大きい
うまくいっていない企業は本当にギャップが激しいです。「あ~これだけ現場と乖離しているから業績悪いんだな・・・」
と思うことが多いですね。まずはこの本社と現場の課題感のずれをきっちりと把握することが最初のステップになります。
店長研修のカリキュラムは課題把握から課題解決案の立案

店長研修のカリキュラムは先述した課題把握の上に成り立ちます。そして、私が持ち帰って店長研修の大枠を作成します。
何より大切なのはカリキュラムを作るまでです。内容が現場とマッチしていなければ受け手である受講生は「何この研修」とネガティブな印象を抱くことになります。
こうなるとなかなかリカバリーするのが難しくなるので、最初の段階の研修プランニングがとても重要になります。
店長研修のカリキュラムを作成しはじめるのですが大きく分けて二つに分類して店長研修をプランニングします。
それは、マインドとスキルです。この二つに分けて研修を立案します。
例えば12回の研修の依頼をもらったらマインド:スキル=6:6なのか5:7なのかの比率を決めます。これはヒヤリング時の各店長のマインド査定次第となります。
マインドとスキルの比率が決まったらコンテンツを作成します。ちなみに最初にマインドをしてからスキル研修へと進めます。はじめにスキルをやって、のちにマインドはないですね。
なぜなら学ぶ姿勢ができていない未熟なマインドをもった受講生にスキル研修をしても右から左に忘れられてしまうからです。
店長研修のカリキュラムのおおよそが決まったら早速研修開始です・・・が、研修も取り組む度にあることに取り組んでいます。それは・・・
店長研修は、必ず指標が明確な課題を出すことが大切

私の店長研修の特徴の一つに難易度がちょっと高めの課題があります。
課題は毎回出すようにしているのですが、この課題が難易度がちょっと高めなのです。課題をやってきたかどうかと同時に、どれだけ生産性が上がったか?まで問うようにしています。
そうすることで、研修を受けただけで満足せずに研修後の結果も出るので「毎回の店長研修価値」が明確になります。
ふわっとした研修でふわっとした課題では生産性は上がらないので明確な指標を決めて取り組むことが大切であると私は考えています。
店長研修の方向性、そしてカリキュラム作成、マインドからスキル、そして研修課題の出し方を今日は紹介しました。ぜひ自社導入の際の参考にしていただけたら嬉しいです。
これからの時代は強い店を作らないと生き残ることができません。強い店とは、景気に左右されずに地域コミュニティになくてはならない店舗を作ることに他なりません。
「もっと早く店長教育しておけばよかった」となる前に早めの準備がお勧めです。その方ができることも増えるし、何より店長の成長が約束されます。
関連記事はこちら

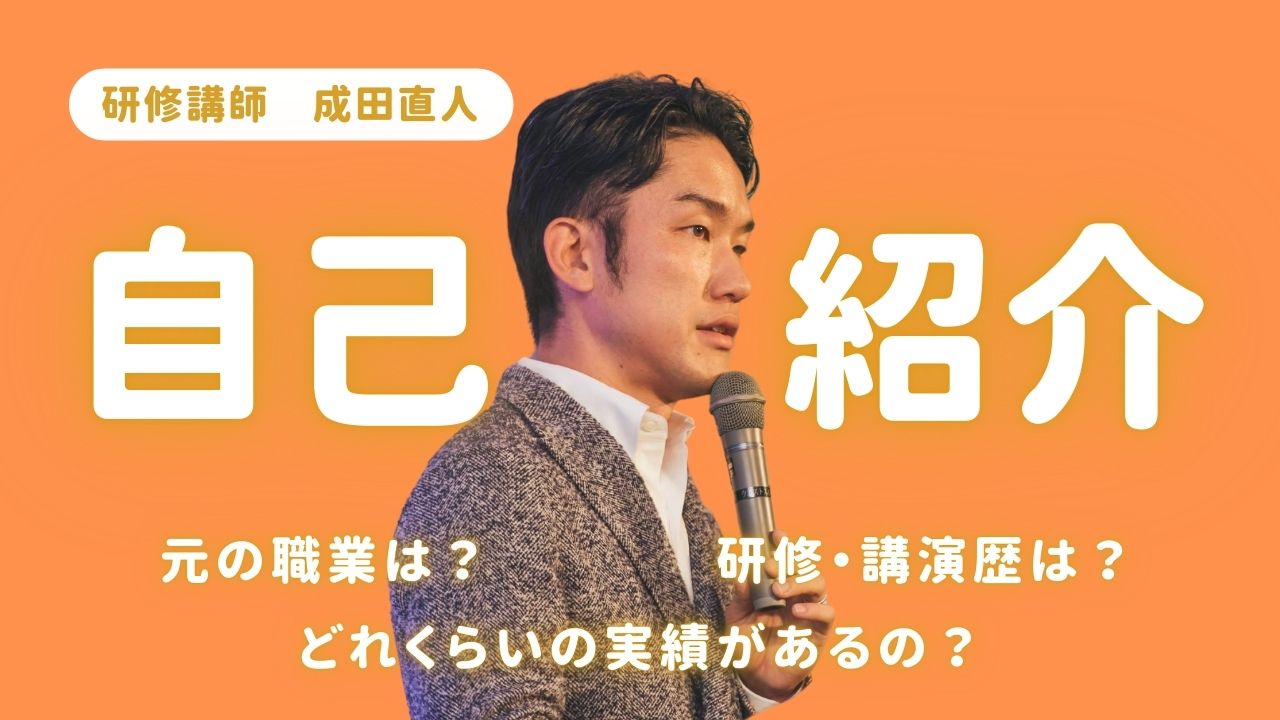


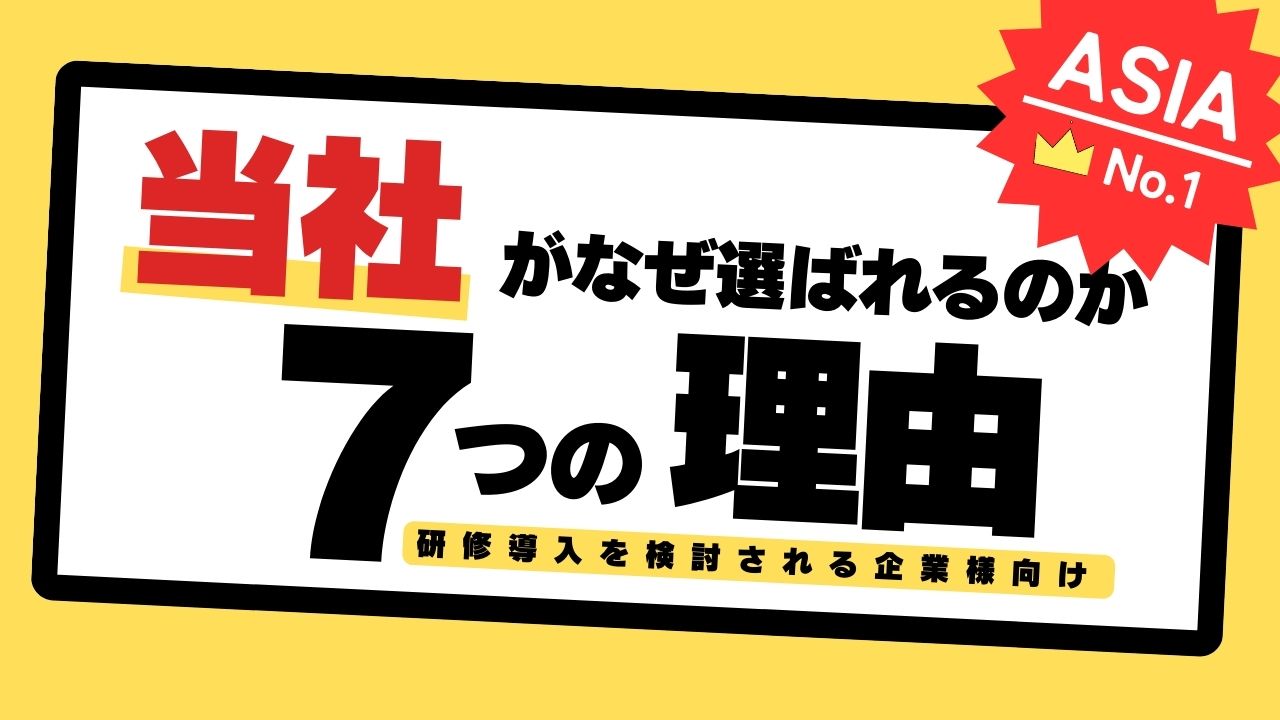
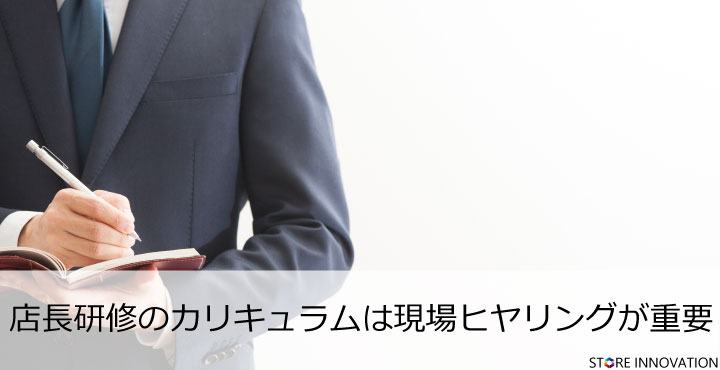


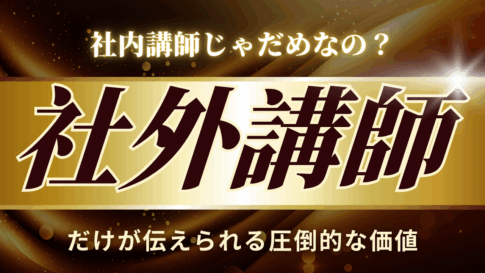
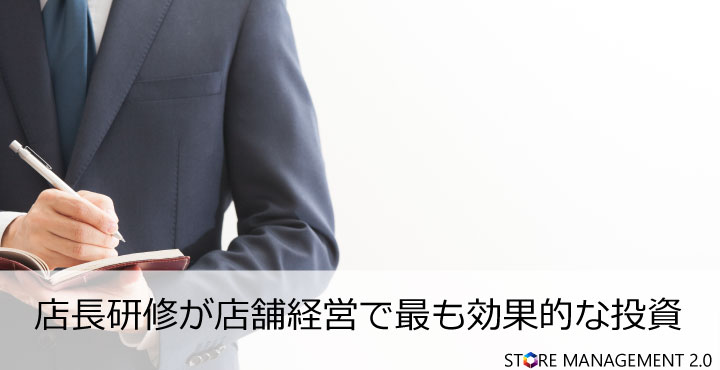
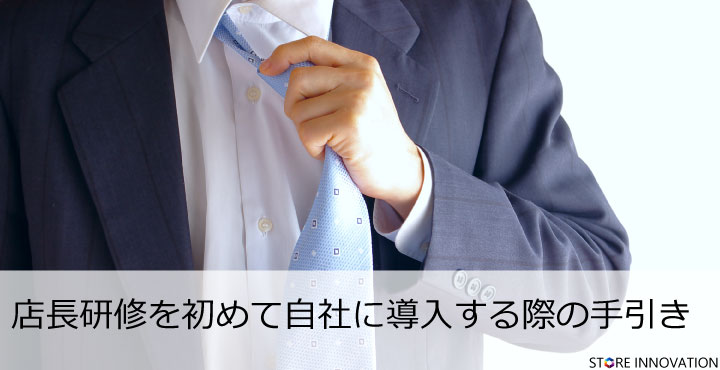
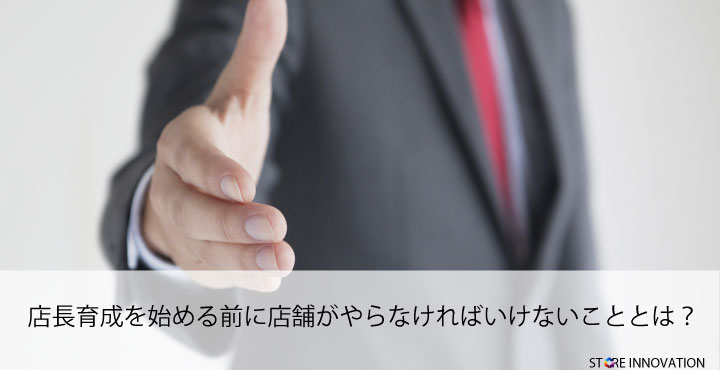


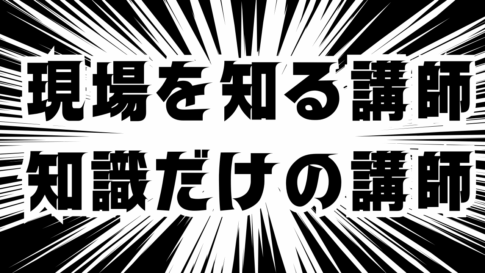
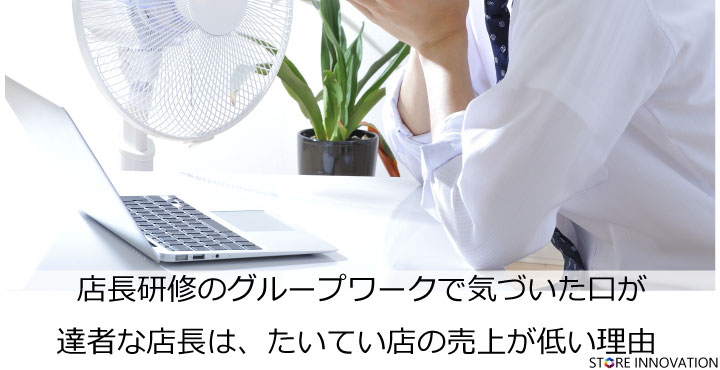
コメントを残す